|
<<ネバリゴシでラーメン>>
 |
 |
1:
小麦粉
小麦粉は岩手県の「ネバリゴシ100%・ひっつみ用」を使います。
「うどんも作ってみるか」で使用した中力タイプの粉です。「ひっつみ」は「すいとん」のことで、この地方ではこう呼びます。
|
|
ラーメンの腰が出るのか、果たしてどうなのか判りませんが、
うどんを作ったときにこれでラーメンを作ったらどうだろうかと思いましたので、試してみます。
座敷わらしで有名な、岩手県二戸市金田一
地区で製造された物です。
|
 |
2:打ち水の計量
かん水に加え、塩と水を用意します。水は浄水器を通した水、塩は海水から作った自家製の塩です。
塩4gを量り、水159gを入れて溶かします。
加水率は44%でやや柔らかめになります。
かん水(35度)を18g追加し、かき混ぜます。塩が溶けにくいので、ていねいにかき混ぜます。
|
|
|
 |
3:粉の計量
ネバリゴシ小麦粉を400g量り、こね鉢に入れます。
|
 |
4:水回し
計量した小麦粉に、打ち水を何等分かになるような感じで、水回ししていきます。
うどん作りでも感じますが、蕎麦よりは水回しが楽な気がします。
箸などでかき混ぜながら、大まかに混ぜていき後は手を使って万遍なく混ぜます。加水率は44%ぐらいになりました。
|
 |
5:水回し終了
水回しが終わりました。これからこね始めます。見た目の色は、強力粉の時とそんなに変わったようには見えません。 |
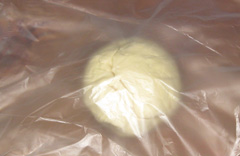 |
6:こねる
ほぼまとまってきたので、これからナイロン袋に入れて足で踏みます。
今回は、やや水分が多いので、踏みやすいと思います。 |
 |
7:こねを続ける
ナイロンの袋に入れて、折り返しながら足でしっかりとこねます。
ムラがなくきれいな一枚の固まりになったら、乾燥しないように袋の口を閉めて一晩おきます。 |
|
今回は常温(平均12〜3℃)で8時間ぐらいおきました。 |
 |
8:のし
充分寝かせたら、のしを始めます。
ここで出来るだけ薄くしないと切るときに苦労しますので、体重をかけてしっかりと
延ばします。
包丁(切る)があまりうまくないので、ここの作業は重要です。
今回は中太麺にするつもりですので、切るときのことを考えていつもより薄くしておきます。 |
|
|
 |
9:のし終了
まずまずの大きさに延ばせました。これで45×55cm位になっています。
端がひび割れましたが、延ばしに時間がかかりすぎたかも知れません。 |
 |
1
0:切り出し
まな板に載せて切ります。
今回は中太麺にするつもりなので、ここが一番肝心です。神経を集中して切ります。 |
 |
1
1:
ちぢれ麺のできあがり
極太のちぢれ麺ができあがりました。
フタをしてご飯の時間まで、6時間ぐらいおきます。
熟成が進んでくれればいいのですが。
1
2:スープもできあがり
並行して進めていたスープづくりがほぼ終わりました。
これも一度休ませて、食べる前に再加熱します。
鶏ガラは、岩手産の
鶏ガラです。このガラは初めて買ったのですが、きそばとうどんでは評判が良かった物です。手元にあったのでとりあえずこれを使います。 |
 |
|
|
|
 |
13:完成しました。試食します。
中太麺なのでゆで時間は3分ぐらいを目安にしました。
トッピングはチンゲンサイとメンマだけ。鶏ガラスープなのであっさり味で、これぐらいが良いでしょう。
|
|
やや歯ごたえが弱いように感じますが、ゆで時間をもう少し短くすれば大丈夫そうです。残りの麺は、ゆで時間を2分30秒にしてみます。 |
|
|
<感想> |
|
強力粉で作ったラーメンとの比較をしようと始めた「中力粉」でのラーメン作りでしたが、やはり違いがあります。加水率等の違いもありますが、腰はやはり強力粉の方があります。さらに、時間が経つにつれてグルテンの変化でしょうか、ちぎれて短くなる部分が多く見られます。
しかし、悪い評価だけはありません。食べた人によっては、「食べやすい。」、「おなかに優しい。」など、このラーメンも好きだよと言う方もいました。
この小麦粉でうどんを作ったとき、非常に延びが良く「ネバリゴシ」の名前はここからきているのかな、と思いました。粉の可能性のような物を感じ、今回はラーメンを試してみました。ピザ生地、餃子の皮なども試してみようと思っています。いろいろ興味の
湧いてくる粉です。 |